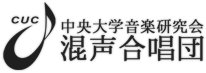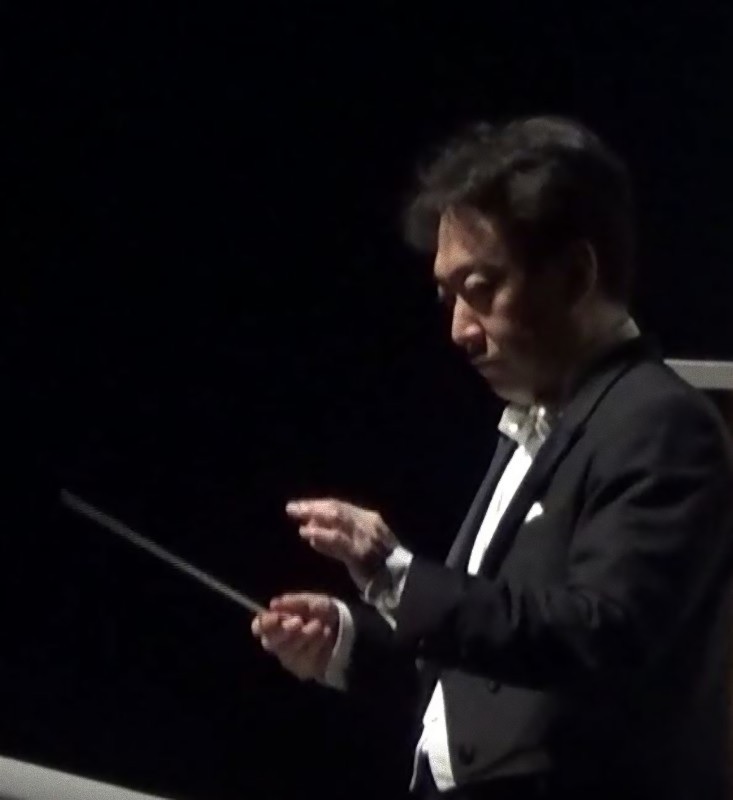 飯坂純<常任指揮者>
飯坂純<常任指揮者>
三重県志摩市出身。武蔵野音楽大学卒業。1996年東京オペラ・プロデュースの稽古ピアニスト、同時期に昭和音大、大学院の伴奏研究員としてキャリアをスタート。2000年笹川日仏財団主催、パリ市立シャトレ劇場での音楽家研修派遣事業に劇場最高顧問J.P.ブロスマン氏より選出され、コレペティの研修を受ける。劇場でのコンサートにも出演、満員の聴衆の中、歌手の伴奏がラジオ・フランスに放送され高い評価を得た。帰国後、新国立劇場小劇場オペラに参加し、2005年、当時の芸術監督T.ノヴォラツスキー氏に実績を認められ、オペラ劇場の音楽スタッフとして抜擢される。主に伊、仏語歌唱におけるオペラのプロンプター、また、その他多くのオペラの副指揮者として公演に携わる。以後、20年間途切れることなく音楽スタッフの役割を担っている。伴奏ピアニストとしての活動の傍ら、指揮も行い、オペラのレパートリーは90作品を超え、特筆すべきは日本初演作品を多く手掛ける、日本では数少ないコレペティ出身の指揮者として注目されている。音楽的啓蒙活動として、カンボジアにおいて初となる、本格的なオペラを上演し、2018年9月プノンペンにて≪カンボジアオペラプロジェクト第一回公演≫「カヴァレリア・ルスティカーナ」、翌年10月に第2回公演「パリアッチ」の両プロジェクトを成功に導く。近年の主な活動は、2018年12月9日、新潟県妙高市文化ホール主催公演にて根本卓也作曲オペラ「景虎」(本邦初演)、2019年2月東京オペラ・プロデュース第103回定期公演グノー作曲「ロメオとジュリエット」を指揮。更に現場での経験を活かし、オペラ制作プロデューサーとしても才を発揮している。NPO法人東京オペラ・プロデュース副理事長/新国立劇場オペラ・プロダクション音楽チーフ/中央大学混声合唱団・常任指揮者/昭和音楽大学・大学院講師。
 中村香里<常任ピアニスト>
中村香里<常任ピアニスト>
国立音楽大学・音楽教育学科卒業。在学中よりオペラ研究団体のピアニストをつとめる。 東京オペラシアター公演『フィガロの結婚』でデビュー以後、『カヴァッレリア・ルスティカーナ』『道化師』『ルイーザ・ミラー』『メフィストーフェレ』(日本初演)などの公演に参加。 千葉市民オペラ公演『ラ・ボエーム』『こうもり』『魔笛』、また多摩市民オペラ公演『トスカ』『蝶々夫人』などの公演に参加。 多摩芸術フェスティバルにピアニストとして参加し、好評を得る。 また杉並オペラ公演『椿姫』、『仮面舞踏会』『愛の妙薬』などの公演に参加。 シド音楽企画主催の『洋楽寄席』『邦人作品演奏会』『日本の音楽展』等に出演。 東京オペラシティにてリサイタルをひらき、好評を得る。コンセール・ヴィヴァン主催の演奏会にも出演。 モーツァルト・ロッシー二などのチェンバリストとしても活躍している。 室内楽、リサイタル共演やオペラのコレペティトゥアとして数多くの公演に参加している。 中央大学音楽研究会混声合唱団のピアニストとして、2006年より参加。
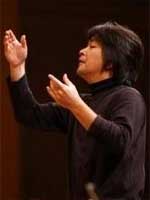 白石卓也<名誉音楽監督>
白石卓也<名誉音楽監督>
1961年高知県出身。1982年国立音楽大学に入学。鈴木惇弘氏に師事。 学生時代より二期会、文化庁オペラ研修所等で副指揮者として多くのオペラの研鑽を積む。 国立音楽大学を中退し、ウィーンに留学、カール・エスターライヒャー氏に師事した。 1986年、シエナ・キジアーナ・アカデミー(イタリア)のオーディションに合格し、ゲンナディ・ロジェストヴェンスキー氏に師事する。 その際、ルッセ交響楽団(ブルガリア)を指揮し、好評を博した。 1991年にはアウディ・ダーティントン・サマーミュージックフェスティバル(イギリス)のオーディションに合格し、その際の演奏にて、ディエゴ・マッソン氏にその音楽性を高く評価された。 中央大学音楽研究会混声合唱団名誉音楽監督。
当団の音楽監督及び前常任指揮者として、28年間(1988~2015年)という長きに渡ってご指導いただきました。音楽面の指導はもちろん、部員一人一人と真摯に向き合うことを大切にされてきました。
子供のような純真さを持ち、練習の度に誰よりも熱い想いで学生にメッセージを送られていたことを、時折ふと思い出します。白石先生は今でも私たちにとって大きな存在であり、その教えは日々の支えになっています。
先生への感謝と、ご冥福をお祈りして。
2017年6月 4年一同