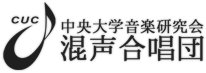■私たちについて/■中央大学音楽研究会混声合唱団の歴史■過去の演奏会
中央大学音楽研究会混声合唱団の歴史 |
|---|
| 記念すべき第1回定期演奏会の日を中大混声が迎えたのは1961年11月22日。 1951年の創立から実に10年もの歳月を要した。 その要因には、この頃の中央大学では女子学生が少なく、「混声合唱団」の体裁を整えるだけの女声メンバーの確保が難しかったことも当然挙げられようが、「歌声喫茶」の隆盛に見られるように「合唱」そのものは、当時の社会風俗として広く定着していたという時代背景もあり、事実、中大混声以外にも合唱サークルが学内にいくつか存在していた。 しかしながらその中には、当時全国的な流行をみた、政治運動の側面を持つ「うたごえ運動」の影響を受けたものも少なくなく、あくまでも合唱を通じた純然たる音楽の追求を志す中大混声がこれらと一線を画したのは、いわば必然であった。 かくして、先行して演奏活動を展開していたグリークラブを始めとする音楽研究会他部会の賛助を受けながらも、演奏団体としての「存在証明」とも言える定期演奏会開催に漕ぎ着けるまでの10年間、粘り強く中大混声を存続させ続けた強固な意思、頑なまでに自らの確信に従うその姿勢こそが、今なお中大混声に息づく活動の原点となる。
やがて音楽研究会他部会の賛助を受けつつ定期演奏会も3回目を数えることとなった1963年、折しも大学合唱団においてプロ指揮者を招聘する動きが広がりを見せていたその頃、一人の団員が一人の合唱指揮者と出会う。 その指揮者の名は、笹倉強氏。翌年からタクトを取った笹倉氏は、中大混声創立当初からの懸案であったプロ演奏家との共演に力を注ぎ、ソプラノ歌手の中沢桂氏を始めとする声楽家による独唱出演を実現する。 そして、在任最後の年となる1968年、日本交響楽団を伴うケルビーニ「レクイエム」演奏までに至った。 5年間という決して長くない在任期間において、現在の中大混声における活動スタイルの基盤を築いた笹倉氏の遺産は、時を越えて今も確固たる足跡を残す。 笹倉氏在任中のとある日、指揮者、山口貴氏との運命の出会いを果たした団員がいた。 山口氏の全身から生み出される音楽に心酔したその団員は、指揮者の交替という音楽団体における最もデリケートな問題に際して当然のように生じる軋轢に臆することなく、己の信念に従うまま山口氏の招聘を断行した。 その団員は、卒団後も監督として山口氏との二人三脚で中大混声の華々しい時代を創出する。 山口氏在任中の18年間、最盛期には200名を超える団員を擁しながら、バロック・古典派から後期ロマン派に至るまでの幅広い年代から多種に渡る大曲をレパートリーとして次々と取り上げていった。 その過程で、山口氏自身が国内初演を指揮したフランツ・シュミット「七つの封印を有する書」の国内3度目となる演奏を1983年に実現し、その年から「真夏の第九演奏会」を毎年開催する。 また、客演の独唱者、独奏者、管弦楽団や後援団体には、アマチュア音楽団体の主催演奏会では凡そ見られることのない錚々たる顔触れが並ぶ、演奏録音盤が音楽誌のレコード評でしばしば紹介されるなど、この頃の隆盛を物語るエピソードは、枚挙に暇がない。テノール歌手の大島博氏、オペラ演出家の大島尚志氏など、卒団後音楽の道に進んだ団員も多数に上り、当時の中大混声が国内クラシック音楽界に与えた影響は、計り知れなかった。 やがて、いつしか軋み始めた歯車の狂いに端を発する団員数の減少により、1986年をもって事実上の活動休止という誰もが予想だにしなかった不幸な結末を迎えたことも相俟って、この時代の記憶が過去に遠のきつつある感も否めない。 だがしかし、山口氏と一人の団員とが手を携えた瞬間から始まり、それから打ち立てられた燦然たる栄達の数々は、紛うことなき中大混声史上の金字塔であり、その輝きは、揺るがぬ一点から時の移ろいを経てもなお光を放つ北極星の如く、今後も中大混声の「現在地」を教え続ける。 1987年12月、中大混声の演奏記録に決して掲載されることのない演奏会が両国公会堂で開催された。 演奏会の名は、「プレ定期演奏会」。 その年予定していた「第5回真夏の第九演奏会」も「第27回定期演奏会」も開催することは、遂に叶わなかった。 眼前の目標を失った中大混声の団員数は、ついに10名足らずとなっていた。 曲目は、彼らが翌年の定期演奏会の演目として決めたハイドン「天地創造」第1部のみ。 チケットが販売されることもなく、客席に関係者以外の人影はなかった。 もちろんプロ奏者による管弦楽団などいるはずなどなく、人づてにようやく探し当てたピアニストのピアノ伴奏による演奏が続く。 この状況で翌年度100人以上の団員を集め、フル・オーケストラで「天地創造」全曲を演奏しようというのか。 これは、誰の目から見ても明らかに「無謀な計画」であった。 事実、周囲にもこの日をもって解散しようと言う者もいた。 それでもなお、解散など考えなかったこの10名足らずの団員がいなかったとすれば、恐らく今も中大混声が存在することはなかったであろう。 タクトを振るのは指揮者、白石卓也氏。 指揮者を失った中大混声は、前任の山口氏在任中からヴォイス・トレーナーを務めるテノール歌手、加藤功氏から白石氏の紹介を受けた。 この単なる偶然に過ぎないとも言える中大混声と白石氏との出会いが、今となっては必然以外の何ものでもないと思えるのが世の不思議である。 現在音楽監督を務める白石氏も、それまで耳にしていた中大混声の世評と目前の現実とのあまりの落差に愕然とし、早々に指揮を断るつもりであったという。 しかしながら、中大混声に残って「無謀な計画」をあくまでも本気で実現したいと言う団員の熱意を受け流すことは、どうしてもできなかった。 かくも、翌年演奏会が実現する見通しすら全く付かぬまま、中大混声の指揮者としての白石氏の険しい道のりがスタートを切ったのである。 予想どおりというべきか、白石氏を招聘した翌年の1988年もハイドン「天地創造」を演奏するに足る団員数は、果たして集まらなかった。 それでも必死で勧誘した1年生や上級生の友人、知人を含む団員数は総勢35人。 もちろん以前と同じく管弦楽団を借切る費用など捻出できようもない。 でも中大混声がこれまでに積み重ねてきた演奏スタイルに決別してしまうのであれば、退部していく何十人もの後ろ姿を目にしながら、何のために中大混声に残ったのか分からなくなってしまう。 ただ歌を歌えればよいわけではないのだ。 そこで少人数でも演奏できるバロック音楽を選択し、小ミサ曲をメイン・プログラムとする「バッハ・アーベント」と題した特別演奏会を開催することとなった。 管弦楽は、白石氏個人の人脈を辿って集められ、楽譜の調達から奏者一人ひとりへの発送も団員が手配し、奏者ごとの譜面台の数に至るまで気を抜けない。 一切の費用を最小限とし、例えばプログラム一つとっても写植を用いず団員が版下原稿を全てワープロで作成した。 かくして前前年までとは比較にならぬほど小規模ながらも、中大混声が長年取り組んできたシンフォニック・コーラスによる演奏会が文字どおり「手作り」によって復活を遂げたのである。 白石氏は、いかなる団員も決して区別することなく一人ひとりの個性を出来る限り掘り起こし、時として本人以上に理解したうえで指導することに心を砕いてきた。 白石氏にとってそれは、人の心と体とが一体の楽器である声楽を指導するために不可欠なものだ。 表舞台から一度は姿を消した中大混声が今や何事もなかったかのように存在するのも、もちろん簡単に団員が集まるからでない。 春の勧誘に成功しながらも冬の大量退部という憂き目に何度か遭いながら、ようやく団員数100名に手が届くところまで追いついた。 新たなスタートラインに立った白石氏と中大混声の挑戦が、既に始まっている。 ***2015年5月追記*** この「ヒストリー」は、これまで中大混声が長きに渡り真摯に音楽に取り組んできたことをより多くの方々に知っていただきたいと思いつつ、白石卓也先生と中大混声のさらなる飛躍を願いながらしたためたものです。 しかしながら突然にも、先生は53歳の若さにして天に召されました。 あまりのことに今の思いを十分にお伝えする言葉が見つかりません。 私もかつて先生の教えを受けた団員の一人でした。先生から学んだことは音楽のみならず、卒団後20年以上を経た今もなお私の人生における普遍的な価値観として息づいています。 この場をお借りして先生からいただいたご恩に深く感謝申し上げるとともに、先生の魂が安らかなることを心よりお祈り申し上げます。 竹縄謙史(当団前監督) |