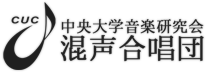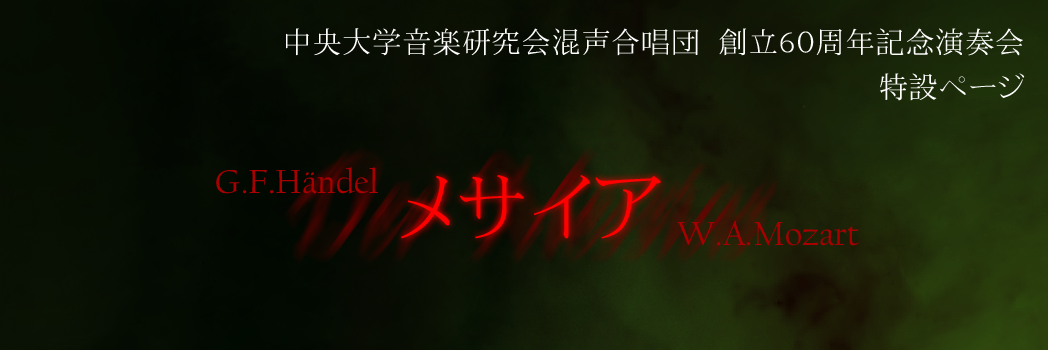
#02 ヘンデルとモーツァルト
(2011.12.02)
ヘンデルとモーツァルト──二人の音楽家が生きた18世紀
ヘンデルとモーツァルト。ヘンデルの生まれは名誉革命とほぼ同時期で、モーツァルトが没するのはまさにフランス革命の嵐の吹き荒れるさなかであった。二人の生きた時代は、市民の立ち上がっていく過程にあったと言えるだろう。音楽の場もまた、宮廷と教会から、市民のための演奏会場へと移っていく――。時代の寵児として愛され、また時代に翻弄されつつ生きた、二人の人生と、その理想を追ってみたい。
| ヘンデル・モーツァルト略年表 | |||||||
| G.F.ヘンデル |
1683 オスマン軍ウィーン包囲 1689 権利の章典 1709 フォルテ・ピアノ発明される 1710 ヴェルサイユ宮殿完成 1725 ヴィヴァルディ『四季』 1727 J. S. バッハ 『マタイ受難曲』 1732 ハイドン誕生 1735 クリスティアン・バッハ誕生 1746 ヴォルテール『哲学書簡』 1748 モンテスキュー『法の精神』 1750 J. S. バッハ没 1762 ルソー『社会契約論』 1767 フラゴナール『ブランコ』 1769 ワット蒸気機関改良 1770 ベートーヴェン誕生 1774 ゲーテ『若きウェルテルの悩み』 1776 アメリカ独立宣言 1781 カント『純粋理性批判』 1789 フランス革命 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | 0歳 | ヘンデル誕生 | |||||
| 1706 | 21歳 | イタリアに赴く | |||||
| 1710 | 26歳 | イギリスへ移住 | |||||
| 1717 | 32歳 | 『水上の音楽』 | |||||
| 1719 | 34歳 | 王立アカデミー創設 | |||||
| 1727 | 42歳 | イギリスに帰化 | |||||
| 1738 | 53歳 | 脳卒中で倒れる | |||||
| 1741 | 56歳 | オラトリオ『メサイア』 | |||||
| 1748 | 63歳 | 『王宮の花火の音楽』 | |||||
| 1752 | 77歳 | 両目の視力を失う | W.A.モーツァルト | ||||
| 1759 | 84歳 | ヘンデル没 | 1756 | 0歳 | モーツァルト誕生 | ||
| 1761 | 5歳 | 初の作曲 | |||||
| 1764 | 8歳 | 渡英、J.C.バッハに学ぶ | |||||
| 1765 | 9歳 | 初の交響曲作曲 | |||||
| 1767 | 11歳 | 初のオペラ作曲 | |||||
| 1769 | 13歳 | イタリア旅行へ | |||||
| 1781 | 25歳 | ウィーンへ | |||||
| 1782 | 26歳 | 結婚 | |||||
| 1786 | 30歳 | 『フィガロの結婚』 | |||||
| 1787 | 31歳 | 父レオポルト死去 『ドン・ジョバンニ』 | |||||
| 1788 | 32歳 | 三大交響曲(39,40,41番) | |||||
| 1789 | 33歳 | 『メサイア』編曲 | |||||
| 1791 | 35歳 | モーツァルト没 | |||||
G.F.ヘンデル
当時の音楽家のほとんどが教会や宮廷の雇われの身分での活動が主だったのに対して、自由の気風の根付き始めたイギリスで、開かれた劇場でオペラやオラトリオを演奏し、進んで一般の聴衆と向き合い、聴衆と共に歩んだ新しいタイプの音楽家であった。
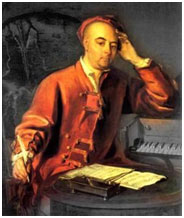
若き日のヘンデル、決闘事件 - 1706年 ハンブルク
オルガニストからキャリアを始め、ハンブルグの歌劇場で活動し始めた頃、ヘンデルは大親友マッテゾンの作品の舞台で、チェンバロを担当していた。作曲家兼歌手として舞台で歌っていたマッテゾンは、自分の出番が終わるとヘンデルのところへやって来て、彼をおしのけて自分でチェンバロを弾きだそうとする。しかし、これに黙っているヘンデルではなかった。そして口論の末、とうとう決闘となってしまう。マッテゾンの剣先が、ヘンデルの胸を突き、あわやと思われたが、当たったのはちょうど上着の金属製のボタンだった。剣は折れ、勝負なしということになったという。音楽のこととなるとことさら熱くなったこの二人は後に和解し、マッテゾンも時の偉大な音楽家の一人となった。
王様との和解の音楽、ヘンデルのための劇場 - 1717年 ロンドン
その後イタリアに旅立ち、当時主流であった音楽家との交流も果たす。一時期はハノーファーの宮廷から楽長として任かれるも、気が進まなかったのか、引き留めるのも無視してすぐにイギリスへ。その当時イタリアオペラが流行っていたロンドンでは、イタリアの音楽を学んだヘンデルは新作『リナルド』を演奏し、予想以上の成功を収める。
しかし、時のアン女王の死後、イギリスの王座についたのはジョージ(ゲオルク)1世、ヘンデルが与えられた任を捨てて去ったハノーファーの領主だった。ジョージ1世との和解のために、ヘンデルは組曲を作り、テムズ川での舟遊びにて演奏する。ジョージ1世はこれを大変気に入り、往復の間に三度も演奏させたという。この組曲は『水上の音楽』と呼ばれ、現代でも名高い。
その後、ヘンデルのオペラを演奏するための団体「王立アカデミー」が設立され、ヘンデルは作曲家、指揮者兼、劇場経営者として激務をこなしていくこととなる。王に認められたことで得た劇場で、ヘンデルは『オットーネ』『ジュリアス・シーザー』など、次々とヒット作を生み出していった。新天地を求めて渡ったイギリスで、彼はついに成功をつかむ。


イギリスへの帰化、王立アカデミーの倒産 - 1727年 ロンドン
しかし、数々のオペラで成功を収めながらも、王立アカデミーの経営は並大抵の事ではなかった。英国でのナショナリズムへの意識が高まる中、ドイツから来てイタリアオペラを書くヘンデルは、だんだんと批判に晒されていく。
ヘンデルは人気を取り戻すために、ついにはイギリスへの帰化を決意する。ここで、ドイツ人「ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル」は、イギリス人「ジョージ・フレデリック・ハンデル」となった。しかし、結局はロンドンの音楽界を二分する勢力争いに巻き込まれ、「王立アカデミー」は倒産に追い込まれてしまう。イタリアからやってきて高慢な態度で技巧をひけらかすイタリア人歌手たちの態度も、イタリアオペラが支持を失った一つの要因だった。
その後ヘンデルは私財をなげうってアカデミーの再建に努め、『アルチーナ』『セルセ』などの傑作を生み出すが、なかなか人気は戻ってこなかった。相変わらずロンドンの音楽界では勢力争いが絶えず、そして気苦労がたたってか、ヘンデルは脳卒中で倒れることとなる。
晩年の奇跡、"メサイア" - 1741年 ダブリン
一時期は死の淵を彷徨いながらも、ドイツに渡っての温泉治療などの甲斐もあってか、ヘンデルは奇跡的に回復しロンドンに舞い戻った。聴衆に再び支持を得るためにはどうしたら良いか――ヘンデルがたどり着いた結論は、イタリア語のオペラではなく、英語によるオラトリオというジャンルだった。
『メサイア』では人々にとって共有のテーマであるイエス・キリストの物語を大胆な感情描写を交えて取り上げ、素朴で力強い英語での合唱は大いに共感を呼んだ。出来映えを試すかのように、アイルランドのダブリンで慈善演奏会という形で始めたオラトリオ『メサイア』の演奏は起死回生の大成功をおさめる。その後書かれた『サムソン』、『ユダス・マカベウス』なども名曲として名高いが、とりわけ『メサイア』は空前の大ヒットとなり、その後幾度も再演は行われることとなる。
貴族たちの趣味に合わせたイタリアオペラを捨てて、市民のためのオラトリオを書き始め、ついにヘンデルは本当の意味でイギリスに受け入れられたのだった。その後、彼は両目の視力を失いつつも音楽活動を続け、最期に倒れた時も『メサイア』演奏中であったという。

W.A.モーツァルト
音楽家であった父レオポルトの熱心な教育と、天性の才能、勉強熱心な性格により幼少期には神童ともてはやされ王侯に人気を博すも、音楽への美学を解さない宮廷や教会に従属的に仕えることによって、自らの望まない音楽を強制されるのをよしとせず、ウィーンでフリーの音楽家としての人生を選ぶ。

出会い、ヨハン "クリスティアン" バッハ - 1768年 ロンドン
父につれられて、モーツァルトは幼い頃からヨーロッパ中を旅して回り、シェーンブルン宮では女帝マリア・テレジア、ヴェルサイユではルイ15世の前でも演奏した。
ジョージ3世に謁見するために渡ったイギリスで、当時人気を博していたのがクリスティアン・バッハ――大バッハの息子である。彼はヘンデルと同じようにイタリアに学びイギリスで成功をつかんだ人物で、しばしばヘンデルの後継者と言われていた。モーツァルトはロンドンでそのクリスティアン・.バッハと出会う。すぐに彼の才能を見抜いたクリスティアンの膝の上で、モーツァルトはクラヴィーアを一緒に演奏し、直接作曲を教わった。このころの最先端の流行は、オーケストラによる"シンフォニー(交響曲)"。モーツァルトは早速、初めての交響曲を書き上げる・・・8歳でのことである。
希望と恋、そして失意 - 1777年 マンハイム
父とともにヨーロッパ中を回りながら作曲と演奏を続けたが、なかなか納得のいく就職先が決まらなかったモーツァルトは、とりあえず父の仕えていたザルツブルク大司教のために働き始める。しかし、音楽にあまり興味を示さなかったザルツブルク大司教の元で働き続けるのにも限界を感じ始める。ザルツブルクではオペラを書く機会に恵まれなかったため、彼は新天地を求めて旅に出る。
たどり着いたのは南ドイツ、マンハイム。芸術に熱心な選帝侯カール・テオドールの治めるその町には、当時最高水準のオーケストラと国民劇場があった。モーツァルトはマンハイムの音楽家たちに認められ、この町での活動に期待する。そして、ここで出会ったソプラノ歌手アロイジア・ウェーバーに、モーツァルトは思いを寄せた。
しかし、選帝侯カール・テオドールはミュンヘンへと移り、宮廷からの仕事を得るのは絶望的になってしまう。またアロイジアとの結婚に父は猛烈に反対し、ついには父からパリに行くように命じられる。そして、パリでは人々から冷遇を受けることとなる――後にマンハイムに再び舞い戻るが、結局就職も恋も実らず、失意のうちにザルツブルクへと帰っていく。


独立、絶対的自信 - 1781年 ウィーン
ザルツブルクに戻り、オルガン奏者として灰色の日々を送っていたモーツァルト。息をするかのように作品を作り続けていた彼の筆が、実に一年近くにわたって止まっていた。そんな彼にチャンスは急に舞い込んできた。ミュンヘンに移った選帝侯カール・テオドールからオペラ作曲が依頼されたのだ。腕によりをかけて作ったオペラ『イドメネオ』は大成功を収める。これを皮切りにして、ドイツ語によるオペラ作曲の試みを、皇帝ヨーゼフ2世から依頼される。オペラの伝統のイタリア語ではなく、自分たちの言葉であるドイツ語による本格的なオペラは、かねてより沢山の人に望まれていたのだ。
「音符はちょうど必要な量だけ使われています。」
これは、こうして作られたドイツ語オペラ『後宮からの誘拐』の初演の際の言葉である。皇帝ヨーゼフ2世が「この歌劇は美しいが、音符が多過ぎるのではないか」と感想を述べたのに対して、モーツァルトは胸を張って答えたのだ。皇帝からの依頼で作曲すれども、従属するのではなく、一芸術家として自らの信念に基づいて作品を書く。ウィーンで可能性を見いだしたモーツァルトは、この町で自由な音楽家として生きることを選ぶ。それまで、あくまでも家臣としてモーツァルトを扱おうとしてきたザルツブルク大司教とは、ここでついに決別することになる。
『フィガロ』と『ドン・ジョバンニ』、栄光と幸福 - 1787年 プラハ
モーツァルトがウィーンでまず身を寄せたのは、折しも実らなかった恋の相手アロイジアの家族、ヴェーバー一家のところであった。そしてこの下宿で新たな愛が芽生える。アロイジアの妹のコンスタンツェ――彼女はモーツァルトの生涯の伴侶となった。
この時代、生活の保証の全くないフリーの音楽家として生きることは並大抵のことではない。音楽教師に、交響曲の演奏会の主催、オペラの上演と、多忙な日々を過ごしつつも、ついに手に実現したこの生活は、彼にとってきっと最も幸せなものであっただろう。そんな中生まれた傑作が、『フィガロの結婚』である。当時の貴族社会に対して大いに風刺的な筋書きのため、ウィーンではなかなか流行らなかったが、プラハでの上演では絶大な人気を博した。翌年の『ドン・ジョバンニ』もプラハの市民からは圧倒的な指示を得ることになる。


フランス革命、天才の晩年 - 1791年 ウィーン
しかし、明るいニュースばかりは続かなかった。最愛の父を、亡くすのだ。厳しくもモーツァルトを導いた父を失うことは、彼にとって大きな衝撃だった。また、『ドン・ジョバンニ』はプラハでの人気の一方で、ウィーンではやはり支持を得ることができない。流行りと廃れの早いウィーンの市民ははじめこそモーツァルトの斬新な音楽に興味を示したが、人間の内面表現するために緻密に書かれた彼の音楽を複雑で難解なものと捉え始めていた。演奏会や楽譜の顧客も次第に減っていく・・・。演奏会などのために借りていた金の返済は慢性的に滞っていた。
そして、フランスでは革命が勃発。激動の時代の始まりであった。先行きの見えない世相に、ウィーンの富裕層の財布の紐はさらに堅くなっていく。また、モーツァルトの音楽に感心を示した啓蒙君主ヨーゼフ2世が死に、大事な顧客を失ってモーツァルトはさらに追い込まれていく。
Coda
満足できる音楽環境を求めて各地を回り、王侯とは重要な関係を維持しつつも一定の距離を取り、自ら音楽のための場を主催し、各地で高まっていたナショナリズムの意識と人生の重要な時期に関わり、聴衆と世相に振り回されつつも自らの信念を貫き通す――二人の生涯を見れば、そのキャラクターと人生の成り行きは大きく異なれど、不思議と符号する点の多さに気がつくだろう。
文学で言えばヴォルテールやゲーテが偉大な人物として尊敬を集めていた時代、音楽家もまた偉業を成そうとした。彼らは、音楽が貴族のためのただの娯楽ではなく、人を描き、人の心を動かす芸術であることを確信し、胸を打つ美しい音楽を追い求めたのだ。
(文責:学術 近藤宏樹)
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |